
以前は「パソコンが使えて凄い」という時代でしたが、今は「パソコンが使えて当たり前」という時代です。
特にパソコンスキルは、事務職の転職には有利という以前に必須スキルであり、使えなければ転職なんて夢物語でしょう。
パソコン系の資格は事務職の業務に必須
パソコンは皆が使えますし、企業のニーズも相当高いです。
となると、パソコン系の資格は「持っていれば有利」ではなく、「持っていないと不利」と言い換えることができます。
最低限のスタートラインにも立てないということですね。
パソコンスキルは事務職以外にも、どのような仕事でも使うと言っても過言ではないのですが、特に事務系では必須のスキルがパソコンです。
事務職の求人を閲覧していると、よく応募条件に「Word・Excelが使える人」と記載されていることがあります。
この一文を見て「よし行ける!」と思う人もいれば「パソコンなんて使えない…」と思う人など、様々です。
ただ、行けると思って蓋を開けたら全然使えませんでしたというのはよくある話であり、結局のところ、「パソコン(Word・Excel)が使える」というのはどこまで使えれば良いのか、という基準があいまいであることがわかります。
それを解消するためには資格を取得するのが手っ取り早いです。
目に見える形で能力を証明していくのです。
資格を取得することによって「パソコンが使える!」と自信を持って就活ができますし、何より目に見える形で履歴書に記載ができるわけですから、書類選考が通りやすくなります。
ですが、よくわからないような団体の資格を取ってもダメです。
資格には知名度がありますので、 知名度の高いものは信頼もされていて人気もあり、何より勉強の過程できちんとしたスキルが身につくでしょう。
わたくしがおすすめする、事務職に役立つパソコン資格はずばり「Microsort Office Specialist」検定と「日商PC検定」です。
以下にそれぞれの特徴を記しておきます。
1.Microsoft Office Specialist(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)
公式サイト MOS公式サイト─Microsoft Office Specialist
概要
通称「MOS試験」。
Microsoftが唯一認める公的資格です。
Microsoftと言えばおそらく知らない人はいないというくらいですが、アメリカの大企業であり、WindowsやWord・ExcelといったOfficeソフトの開発元であります。
その開発元が唯一認める公的資格なわけですので、有名かつ強力と言えます。
試験レベル
指示された機能を使って問題を解く試験ですので、指示された機能を使わなかったり、指示された場所に機能を適用しないと全て誤答となります。
言い方を変えると「採点マシンのご機嫌取り試験」とも呼べます(笑)
レベルは3級、2級…というような数字ではなく、「Specialist(一般)」と「Expert(上級)」という風に表されます。
事務職であればSpecialist(一般)で十分通用します。Expert(上級)の出題範囲の機能はマニアックすぎて、実務では使用しない会社がほとんどです。
Microsoftの社員しか使ってないんじゃないか?というような機能がてんこ盛りです(笑)
しかもSpecialistより値段が若干高いため、まさに自己満足と言えるでしょう(パソコンの講師になる等なら別です)。
試験科目(ソフトの種類)
Word、Excel、PowerPoint、Accessの4種類がメインかつ有名どころですが、このうちWordとExcelを取得していれば問題ありません。
何せ日本の企業の9割はこれら両ソフトを使って仕事をしているという統計が出ています。
PowerPointとAccessに関しては…その時の状況に応じて取得すれば良いでしょう。
地域や職種によっても必要とされているか否かは分かれてきます。
またソフトにはバージョンがあります。
どの会社がどのバージョンを使っているかなんてことはわかりようがありませんので、2010か2013バージョンを取得しておくのが無難と言えます。
新しいソフトは企業が導入していない可能性が大ですし、2010と2013はさほど違いがなく企業も導入を控えているところが多いため、どちらを取得しておいても十分通用します。
ただし2017年12月現在、最新バージョンは2016ですが、2016は企業でもほとんど浸透していませんので、取得する必要はないと言っても過言ではありません。
まとめると、Specialist(一般)レベルのWordとExcelの2010か2013バージョンを取得すればOKということです。
ただし操作方法は違いがありませんが、試験の出題方法に大きく違いが分かれます。
2010は一問一答型(前の問題が次の問題に影響しない)に対し、2013は成果物完成型(前の問題の操作が次の問題にも影響する)ので、2013の方が若干難しいと言えます。
長所
- 機能さえ覚えれば良いので、タイピングスピードはあまり関係ない。
- 機能の詰め込みで受かる可能性がある(※おすすめしません)。
- 俗に言う「Word・Excelが使える方」に該当する。
短所
- 試験料が10,000円越えと、少々お高い。
- ソフトの種類とバージョンが様々なので、どれを取得したらいいか迷う(バージョンは今現在でしたら2010か2013がおすすめ)。
- 機能の詰め込みになってしまいがちで、実践で使えるとは言い難い場合も。
- 機能の確認試験のため、機能や手順を指定されている問題が多く、操作結果が同じでも手順次第では不正解になることもあり、色々な操作方法を知っている人にはもどかしい。
2.日商PC検定試験(文書作成、データ活用)
公式サイト 日商PC─商工会議所の検定試験
概要
日本商工会議所が主催しているパソコンの検定試験です。
以前ワープロ検定などという一般的な名称で高い知名度を誇っていましたが、平成18年ごろに名称や試験方法が変わっています。
なお、表計算はビジネスコンピューティング試験と呼ばれていました。
試験レベル
レベルは3級~1級まであり、上述のMOS試験は機能の試験に対して、こちらはその機能を駆使していく応用の試験という位置づけで、より実践的な内容になっています。
ですから、自分が知っている機能をどのように使うのか、つまり機能の使いどころをきちんと把握していて適切に使えるかが試されるため、操作過程(使った機能)より成果物(完成品の出来)が重視されます。
3級でも充分だとは思いますが、2級まで取得できればかなり実践力はついていると見られます。
筆者も取得しておりますが、2級は民間のパソコン資格の中ではかなりレベルが高いです。
自分のパソコン力を高めたいとお考えの方は、MOSを取得した後にこちらの資格を取得されると良いでしょう。
試験科目(ソフトの種類)
こちらはMicrosoftの公的資格というわけではなく、あくまでワープロや表計算ソフトの技術をテストするものです。
また数年前に新しくプレゼンテーション能力の試験も導入されました。
ですからどのソフトを使用してもいいのですが、ほとんどWordやExcel、そしてPowerPointを使用して試験に挑むことになるでしょう。
それぞれのソフト(カテゴリ)の名称がカッコ書きでつくのが特徴で、たとえばワープロ(Word)の3級であれば「日商PC検定試験(文書作成)3級」という名称になり、表計算(Excel)の2級であれば「日商PC検定試験(表計算)2級」となります。
長所
- 機能を問わず文書等を仕上げていくタイプの問題なので、自分の知っている機能を駆使して解答を仕上げていくことができるため、応用力や実践力が身に付く。
- 知識問題もあるため、パソコンの知識自体も身に付く。
- 試験代もそれなりに抑えられている。
短所
- MOSと比べるとやや難易度が高い。
- 知名度がMOSや昔のワープロ検定等と比べると今一つ。
- 受験できる会場がやや少なめ。
両試験共通のおすすめ事項
試験がパソコンで行われるため、試験終了と同時にコンピュータが採点をし、その場で合否がわかります。
つまり合格した方は画面に「合格」と出るため、その場で履歴書の資格欄に記入することが可能になります。
即効性の非常に高い試験のため、急いでいる方にも、そして手軽に手っ取り早く資格を得たい方にもおすすめです。
終わりに
機能重視のMOS試験、実践重視の日商PC検定と住み分けができるですが、やはりMOS試験の知名度が高すぎます。
まずMOS試験を取得して機能を覚えてから、その覚えた機能を日商PC検定で活かしていく、という流れが一番パソコンの実力をつけられます。
他にもP検やシスアドなど国家試験もありますが、事務職ならば上記の2つのどちらかを押さえておけば充分です。
そして最後に、事務職にはWord・Excelがどの程度使えればいいのかをまとめましたので、こちらもご覧いただければと思います。

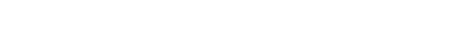



コメント